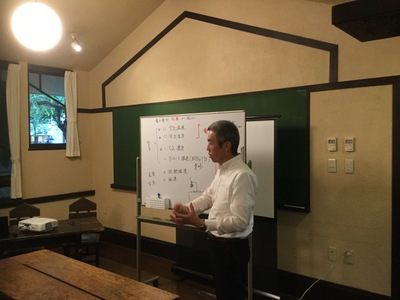さる6月15日2018年度の総会がいつもの会場の池袋明日館で開催されました。2017年度の報告と2018年度の活動計画について無事承認され2018年度6期目がスタートしました。
勉強会は、当会顧問である高知工科大の田島先生により「換気システムの維持管理に関する検討の最新情報」と題した講演です。最初に最近、プランニングによる空気室や温熱環境への影響について研究しており、特に廊下の計画が影響が大きそうだという興味深い話から始まり、換気の設計・計画、お客さんの換気に対する意識認識からメンテナンスや清掃をおろそかにしていると機械換気システムは風量の低下や消費電力の増大といった影響が出てくることの説明があり、いかにメンテンナンスをしやすくするか?そのためはシンプルなシステムほどアドバンテージがあることが説明され、そのメンテナンスに大きなアドバンテージがあるパッシブ換気のよさを再認識する講演となりました。
続いて北海道大学の菊田先生による「パッシブ解析ソフトの活用方法」の使い方の勉強です。解析ソフトは北海道大学が作ったパッシブ換気の設計を行うためのソフトです。つづいての「これからの住宅に求められる環境技術いついて」と題した講演で、エネルギーの考え方からエアコンの特性や選び方の判断の仕方など基本から応用まで教えて頂き、後半では北海道の事例で超高性能パッシブ換気住宅の事例報告として、外気を地熱で温めるアースチューブの代わりに最近採用例が増えている太陽熱集熱パネル(ソーラーウォーマー)の効果について実測検証の結果についてお話しいただきまた。パッシブ技術を活用すると熱交換換気にも匹敵する性能を得られる事が解り、パッシブ換気の優れた点をまた理解することが出来ました。
第四部ではパッシブ換気の効果をお客様に示すために様々な測定をして学術的にも表示できるようにしたいということで、本州と北海道のそれぞれ実測に携わっていただいている田島先生と菊田先生に測定方法の共通化ルールについての検討をいただきました。今後様々なデータで示すことが可能になると思います。
最後は全員による近況報告や最近の取り組み等の発表で相互に情報交換を行い、最後に事務局から国立保健医療科学院の林先生と当会との共同研究で得られた「サーマルダンパーを用いたパッシブ換気の特性」で、温度差が少なくなる中間期に換気量を増やす手法についての研究結果の報告もあり、大いに身になるになる総会となりました。